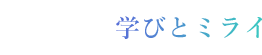模試の活用法 ~東大生ブログ、AI回答、学問ノススメ~
- 2025.08.8 | 高校生・受験生の学び(現在)
模試の活用法
何度も受けている模擬試験。その活用法について、東大生のブログ、AIの回答、最後に学問ノススメの考えを紹介します
東大生のブログ
東大生学生サークル FairWindのブログ記事を紹介します。
模試の前、模試当日、模試の後の3つに分けて説明しています。一人の東大生のブログに過ぎないので、参考にするもしないもあなたの自由です。私が面白いと思ったことは、模試の当日の動きです。とても細かいルーチン(用意するシャープペンシルの芯の本数)を決めているのですが、細かなことではなく、その背景にある考えに共感しています。試験本番を見据えて、本番で余計なことを考えず実力が発揮できる状態に持っていくことをしっかりと考えて模試を利用していることです。広く言われている「間違った問題の解き直しや復習」ではなく、模試の目的は、「本番で100%実力が発揮できるように練習すること」と、考えて臨んでいることです。

AI(Chat GPT)の回答
AIに以下の質問をしました。
大学受験の模試を高校生が受ける際に、模試の前、模試の受験時、模試受験後に心がけておくことは何だと思いますか?ライバルの受験生と差をつけるために効果的な対応を教えてください。
AIの回答
(少し長いですが、AIの能力を知るうえで、参考になると思いますので、全文を紹介)
大学受験において模試(模擬試験)は、自分の実力を測る絶好の機会です。ただ受けるだけでなく、戦略的に活用することでライバルと差をつけることができます。以下に、「模試の前」「模試の受験時」「模試の受験後」のそれぞれで心がけるべきポイントを、差をつけるための視点から具体的に解説します。

【模試の前】準備段階での差が本番の成果を分ける
1. 「模試の目標」を明確にする
・ 「今回は時間配分に慣れる」
・ 「数学は全問解くのではなく、完答できる問題を増やす」
・ 「英語長文を15分短縮して読む」など
→ 目的意識を持って臨むだけで、集中力・再現性が高まります。
2. 過去の模試や過去問で“演習の型”を作っておく
• 模試の形式に慣れておくこと。
• 特に共通テスト型模試なら「時間配分の感覚」が命。
→ 時間を意識した演習を繰り返し、得点力の底上げを図る。
3. 事前に「苦手分野」を明確化して挑む
• 苦手な単元(例:古文の敬語、数列の漸化式など)を前日までにピンポイントで復習。
→ 「今回はこの単元を克服する」と意識することで、意識的に得点アップを狙える。
【模試の受験時】本番で差がつくのは“実践力”と“冷静さ”
1. 時間配分の練習通りに実行する
• 「最初に解ける問題を選び、最後まで見通す力」が大事。
→ 焦って最初に時間をかけすぎない。時間切れで失点するのが一番もったいない。
2. 途中で心が折れても立て直す
• 模試では「中盤で失敗しても後半で巻き返せる力」が求められる。
→ 精神的な持ち直し方も受験の力。落ち込まず、次の科目でリセット。
3. 見直し時間を必ず確保
• 時間に余裕ができたら、計算ミスやマークミスをチェック。
→ 本番でも使える“点を落とさない習慣”を身につけることができる。

【模試の後】ここで差がつく!模試は“解き直し”が本番
1. 全科目「解き直しノート」を作る
• 「間違えた理由」「なぜその選択肢を選んだか」「どうすれば解けたか」を記録。
→ 反省と再現の記録は最強の学習資料。模試1回で成績2回分の成果を得られる。
2. 「なんとなく正解だった問題」も徹底分析
• 運よく正解した問題を放置すると、本番で再現できない。
→ 本当に理解しているかを検証し、曖昧な知識を潰すことが差になる。
3. 模試結果をもとに“戦略”を調整する
• 得点のバランス(国語だけ高い・数学が足を引っ張るなど)を分析し、今後の勉強計画に反映。
→ 受験は“戦略勝負”。模試データは最良の羅針盤。

まとめ:ライバルと差をつける模試活用法
模試前: 目標設定・苦手潰し・時間配分練習
模試中: 精神の安定・実践的判断・見直し習慣
模試後 :解き直し・原因分析・学習戦略への活用
模試は「受けること」ではなく「活用すること」で差がつきます。偏差値や判定は大事ですが、それ以上に「どう行動したか」が合否を左右します。模試1回を“自分だけの特別講義”に変えていきましょう。
希望があれば、解き直しノートのテンプレートや記録用のフォーマットも提供できます!
学問ノススメの考え

1.模試は練習試合
練習試合で目標にすることは、勝つことではなく、本番に備えたチェック。その意味で東大生の言っている考え方「本番に普段の実力が出せる」ために、実験をすることです。この意識を強く持って模試に臨めば、模試での失敗は、本番の成功につながります。実験することを、自分で考えて自分で戦術を立てることを楽しんでください。模試の前日や当日の休み時間のルーチン、試験中の問題の解き方・時間配分など、試すことは人それぞれ、山ほどあります。
2、模試に備えた準備学習は不要
模試は点数をあげることが目標ではなく、上記の本番に備えた練習以外には、現在の学力の足らざるを見つける限られた機会として活用してください。直前の勉強は無用です。理解せず暗記しているだけでは、本番で忘れています。今の実力を測ることができれば十分です。
3.模試受験後は足らざるを肝に銘じる
模試の解き直しを目的意識を持たずにやることは無用。どの理解が定着していなかったのか、理解していたけど出来なかったのはなぜか(時間が足りなかったのか、ケアレスミスか)自分が納得できるまで振り返れば十分です。解き直しをしなさいという指導は、個々を分析していない浅い指導です。試験の復習で、足らざるところを少しでも多く見つけ出して、以降の学習に結び付けていくこと、これがPDCA(Plan Do Check Action)のCheck Actionです。
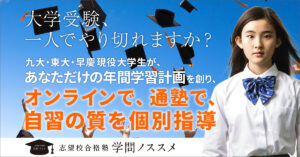
総評すると、東大生の生の経験は、AIの平板なアドバイスに比べて、数段優れています。受験生の血肉になるアドバイスです。AIの一般的な使い方ではこういう結果になることが通常です。より突っ込んで質問をすれば、良いアドバイスにたどり着くこともありますが、現在は成功者の経験知に軍配があがります。
理解していただけたでしょうか?学問ノススメの個別指導の無料体験をして頂くことで、個の指導を実感して頂けると思います。
(文責:学問ノススメ 大井 臨床発達心理士 詳しい経歴はコチラ)