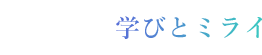大学受験とAI活用 ~英語の勉強法 その2~
- 2025.09.19 | 高校生・受験生の学び(現在)
大学受験とAI活用~英語の勉強法 その2~
大学受験勉強とAI活用についてのブログ。前回は”大学受験の英語勉強法”について、「参考書の選び方や、単語・文法、読解、リスニング、英作文のそれぞれについてのAIの回答」について説明しました。今回は英語の勉強法について、さらにAIに追加質問した結果を説明します。AIの実力を知り、AIを大学受験勉強に活かすための参考になると思いますので、少し長い文章ですが、参考にしてください。
AIへの追加質問
回答ありがとうございました。頂いたアドバイスについて、以下の2点について、教えてください。
1.日本人が「外国語である英語」を学習するという視点での注意点
2.認知心理学的に人間が言語を学ぶという視点での留意点
学術的な視点での合理的な言語学習が大切と考えての質問です。どうぞよろしくお願い致します
AI(Chat GPT)の回答

こちらこそ丁寧なご質問ありがとうございます。学術的な視点で学習の合理性を考える姿勢は、非常に本質的で、長期的に効果的な学びにつながります。ご質問の2点について、それぞれ分けてお答えします。
1.日本人が「外国語としての英語」を学ぶ際の注意点
・言語間の「距離」の問題
- 日本語と英語は**言語的距離(typological distance)**が非常に大きい言語同士です。例:語順(SVO vs SOV)、冠詞の有無、時制体系、語彙の起源など。
- この距離の大きさのため、日本人にとって英語は「習得に最も時間がかかる言語の一つ」であることが、アメリカ国務省のFSI(注)などからも示されています。
(注)Foreign Service Institute 米国国務省で職員(外交官など)に外国語教育等を行っている機関。日本語は習得までの時間が多く必要な外国語で、難易度が最も高いカテゴリーVに分類されている
・注意点:
- 英語を日本語の感覚で「直訳」しない訓練が必要。→構文(SVOC)や語法をしっかり理解すること。
- 文化的背景の違いも学びの障壁になるため、背景知識(文化、論理構造)も吸収する意識が必要。
・日本人特有の「学校英語」バイアス
- 多くの日本人は中学~高校で文法中心の英語を学び、「テストのための英語」になりがちです。
- そのため、以下のような現象が起こります:

| 学習の問題点 | 理由 |
| 聞けない | 音声訓練の不足。スペルから発音を想像するクセ |
| 話せない | アウトプット経験の極端な不足 |
| 書けない | 自分で考えて英語を書く経験がない |
| 読めない | 単語の意味を拾うだけで構文がとれていない |
・対策:
- 読解・文法と並行して、音声(リスニング・シャドーイング)や英作文を早い段階から取り入れる。
- 4技能のバランスを意識する。
- 日本語との違いを理解し、英語を「英語のまま」処理するトレーニング(例:返り読みせず、前から訳す練習)
2.認知心理学的に言語を習得する際の留意点
・短期記憶 vs 長期記憶の違い
- 人間の記憶は短期記憶(ワーキングメモリ)と長期記憶に分かれます。
- 言語習得では、短期記憶で理解→繰り返しによって長期記憶に移行する必要があります。
・留意点:
- 単語や構文は1回で覚えることを期待しない。→エビングハウスの忘却曲線に従い、反復(復習)間隔を戦略的に設計する。
- 「分かったつもり」=短期記憶。→実際に使って(アウトプットして)初めて長期記憶に定着する。

・マルチモーダルな入力が記憶を強化する
- 単語や文法を「視覚」「聴覚」「運動感覚(書く・話す)」など複数の感覚で学ぶ方が定着しやすいことが実証されています。
・留意点:
- 単語を覚えるときは、「音声を聞く」「発音する」「書く」「文脈で使う」など複数の刺激を組み合わせる。
- 音読やシャドーイングは脳の複数領域を刺激する学習法として有効。
・理解より「自動化」がゴール
- 認知心理学では、熟達者(エキスパート)は処理の自動化により負荷を軽減しているとされます(例:Chase & Simon, 1973)。
・留意点:
- 文法や構文理解も、最終的には「考えなくても自然に使える状態(自動化)」が目標。
- そのために、**「理解 → 模倣 → 練習 → 応用」**の段階的プロセスが必要。
・生成(ジェネレーション)効果
- 「情報を自分で思い出して再現(生成)することで、記憶が強化される」という効果です→例えば、単語の意味を見て思い出すより、「意味を見て単語を自分で書く」ほうが記憶に残る。
・留意点:
- 暗記カードやクイズ形式の復習、英作文などアウトプット型の学習を重視する。
- 「読むだけ・見るだけ」の勉強は定着が弱い。
・まとめ:合理的に英語を学ぶための5原則
| 原則 | 内容 |
| 1.理解と自動化を分けて考える | 理解はスタート、反復練習で自動化することがゴール |
| 2.インプットとアウトプットをバランスよく | 読む・聞くだけでなく、書く・話すも必須 |
| 3.繰り返しが最大の記憶法 | 「間隔をあけた反復」が効果的(忘却曲線に従う) |
| 4.多感覚を使う学習を心がける | 視覚・聴覚・運動感覚の併用(音読・書くなど) |
| 5.日本語との違いを意識する | 構文・語順・文化・発音の違いを認識して吸収する |

学問ノススメの総評
1.質問内容を更に深堀りする際に、私が英語学習にとって重要と考えている2点に絞って質問しました。
2.英語の参考書や講師ブログなどで頻繁に取り上げられている内容を回答していますので、参考にはなります。例えば、
- 日本語と英語の言語間の距離
- 学校英語バイアスとその対策
3.ただし、多く公開されている情報を中心にロジックを展開しているので、目新しいものはありません(AIの回答はその特性から当然そうなります)中には、深く大学受験英語を考えた回答ではないものもありますので、注意が必要です。
4.例えば、日本人高校生が外国語として学んできた英語のレベルを問う試験(大学受験)では、文化的背景の違いが障壁となることはほとんどありません。背景知識が必要になるのは、ビジネスや学術分野で英語を使いこなしたり、あるいは、現地で母国語話者と生活をするレベルまでを求められる場合です。この点は明らかにミスリードした内容です(注:多くの塾や予備校の英語指導法でも文化的背景の理解の重要性を頻繁に指摘しているので、その情報を拾ってくるAIとしては仕方がありません)
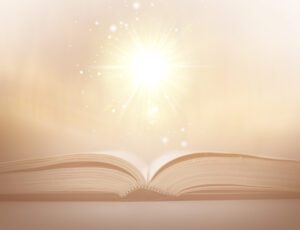
4.認知心理学的視点でのコメントになってくると、言語習得について学問的に明確に確立された理論があるわけではないので、とたんに浅いレベルの回答となってきます。学術的に言語習得で述べられている言説を羅列したものになっています。例えば”短期記憶と長期記憶(忘却曲線)”、”マルチモーダルな(五感を活用した)入力”、”生成効果(自分で生み出す努力)”です。
5.これらの言説(理論)は参考になるのですが、それらを意識した学習法となると理論と実践を結び付けることのハードルが高いので、自信にあふれたアドバイスではなくなっています。これも、人間が未だ解明できていない記憶や言語習得のメカニズムをAIが解説できるわけがないので、当然の帰結です
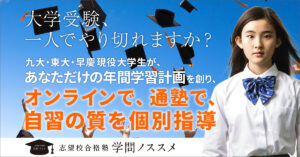
次回は、AIの回答も踏まえた上で、言語習得という人間の活動の未知の分野にどのように臨むのか、特に”大学受験における外国語習得”という視点での”効果的な英語学習法”について、学問ノススメの考えをご紹介させて頂きます。
(注)学問ノススメの個別指導の無料体験をして頂くことで、学問ノススメの受験勉強へのアプローチや考え方、個の指導を実感して頂けると思います。どうぞお気軽にお問い合わせください。
(文責:学問ノススメ 大井 臨床発達心理士 詳しい経歴はコチラ)