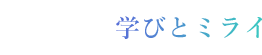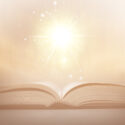AI とバカの壁
- 2025.10.31 | 未来への学び(遠い未来)
FUKUOKA AI Education 〜Google Geminiと学ぶ 1Dayキャンプ〜
Google の生成 AI ツールである「Gemini」を活用した学びの可能性を探求する一日として「FUKUOKA AI Education 〜Google Geminiと学ぶ 1Dayキャンプ〜(10月19日)」に参加しました。このセミナーは、福岡未来創造プラットフォーム(注)が主催しました。
(注)いわゆる産官学連携による取組、2019年5月に開始。福岡市を中心とする高等教育の振興と地域社会の活性化を目的に福岡都市圏に位置する大学・自治体・産業界で「福岡未来創造プラットフォーム」を形成し、個々の資源を共有するとともに大学・自治体・産業界の垣根を越えた取り組みの実現を目指しています。(同ホームページより)高校生向けの活動としては、福岡のまちと大学の魅力を全国の高校生に向けて発信するウェブサイト”DAiFuk.“を運営しています。
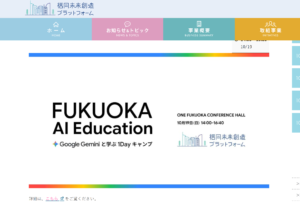
メインスピーカー(浜崎洋一郎さん、システム開発会社副社長)から、AIの技術力の進歩やビジネスでの活用についてプレゼンテーションがあり、Google社からはGeminiの機能紹介、最後に九大生他福岡の大学生によるAI活用の事例についての説明とパネルディスカッションが行われました。印象的だった内容は、以下の通りです。
1.AIの学習能力(注)が2022年から2025年の間に爆発的な伸びを示している
(注)パラメータ数(*);3,550億(2022年)→52兆 (2025年)
(*)AIが学習中に”最適化する変数”の数を指します。これらの変数は、モデルが入力データを処理し、予測や生成を行う際に使用されるものです。AIの知識量を示す数値と言えます
2.大学生は研究や生活でAIを積極的に活用していますが、「AIに質問を投げっぱなしは嫌!」「良い距離感を保っていたい」という発言があったこと
バカの壁
バカの壁は養老孟司さん(東京大学医学部名誉教授)のベストセラー(2003年の流行語大賞)。わかったつもりで思考停止することを「バカの壁」と称し、「情報過多の時代に生きるヒトの生き方」や解剖学者の知見から「人がわかるうえでの身体性」について記した内容になっています。
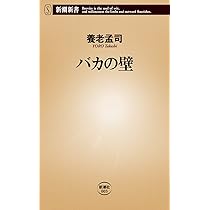
(Amazonより)
今回のAIセミナーの参加で、養老孟司さんのバカの壁が思い浮かびました。養老孟司さんは、最近の著書「AIの壁 人間の知性を問いなおす 」でもAIと人間の知性について、いろいろなジャンルの専門家(棋士の羽生永世名人、数学者、哲学者、経済学者)と対談をしています。また、大阪万博では「AI養老先生と本人の対談」をして話題になりました。同対談では、AIとの対話(南海トラフ地震への対応がテーマ)について、「違和感はない」と発言しています。「わかること」について身体性や経験の視点を考え抜いている養老先生が、「違和感はない」という発言をされたことがとても興味深かったです。

(AI養老先生と本人の対話:佐賀新聞より)
問いをたて、わからないことを楽しむ
今回のAI活用セミナーで、養老先生の「バカの壁」がまず浮かんだのは。「問いをたてる」力、「バカの壁があること」を認識できる力、「考えることを放棄しない」力が、AI時代を生きていく人間に求められ知性だろうと考えたからです。
みなさんは、受験勉強において、AIを活用してわからないことの解答を容易にみつけることができます。どんどん活用してください。一方、自分で問いをたてる努力、わからないことを楽しむ姿勢、という人間の特性を意識した学びが求められているのだと、今、考えています。問いをたてる努力、わからないことを楽しむ気持ちを大切にしてください。
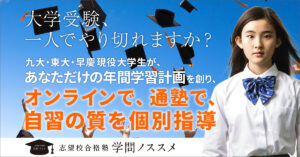
【文責 大井 筆者の略歴はコチラ】