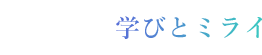大学受験とAI活用 ~英語の勉強法 その3~
- 2025.10.3 | 高校生・受験生の学び(現在)
大学受験とAI活用~英語の勉強法 その3~
大学受験勉強とAI活用についてのブログ。過去2回は、1.大学受験の英語勉強法”について、「参考書の選び方や、単語・文法、読解、リスニング、英作文のそれぞれについて」のAIの回答 2.英語の勉強法について、AIに質問を深堀りした結果(日本人が「外国語である英語」を学習するという視点での注意点、認知心理学的に人間が言語を学ぶという視点での留意点)を説明しました。最終回は、AIの回答も踏まえた上で言語習得という複雑な人間活動の分野にどのように臨むのか、”大学受験における外国語習得”という視点での”効果的な英語学習法”について学問ノススメの考えを紹介します。

(1).AIのアドバイスについてのまとめ
以下の2点がAIアドバイスに関する私の意見です。
1.参考書の選び方、単語・文法、読解、リスニング、英作文のそれぞれの学習法について、ネット上広く有効と認められている情報をまとめているのでAIの回答を参考にできる
2.認知心理学的に人間が言語を学ぶという視点での留意点について、日本人が英語を学ぶという分野(=学問的には専門的(狭い範囲)研究分野)になると、深く掘り下げたアドバイスをAIから吸収することは困難な現状(∵認知心理学的に高度な研究。確立した理論がなく公開情報も限定的。応用範囲が限定的であるので、AIが一般化することは苦手な分野)
(2).学問ノススメの考え
上記(1)について、AIの意見を補う際に注意した点は以下の3つです
1.言語習得についての認知心理学・言語学の理論
2.外国語習得についての理論
3.大学受験の英語という視点での実際的な学習

1.言語習得についての認知心理学・言語学の理論
認知心理学・言語学上の主な理論は、生得論、行動主義的学習理論、社会相互作用理論です。
1.生得論:人間には生まれながらに文法装置(LAD: Language Acquisition Device)」が備わっているとする立場。赤ちゃんが言葉を覚え急激に高度な段階まで発達するには、言語特有の生得的な条件が備わっていないと説明がムツカシイという理論的な背景があります
2.行動主義的学習理論(環境的要因);言語は特殊な能力ではなく、一般的な学習メカニズム(条件づけ・強化学習)に基づいて習得されるという立場
3.社会相互作用理論:言語は他者とのコミュニケーションの中で発達する。環境と社会的文脈が重要という立場
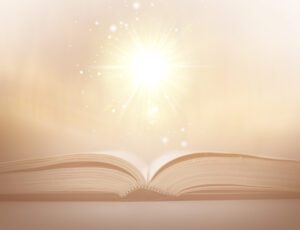
3つは対立的な理論ではありますが、一つの理論で説明できるものではなく、生得的要因、環境的要因、社会的要因が複合的に働いているという論説が現在は有力です。詳しい説明は、以下の質問をするとAIがすぐ答えてくれますので、興味があれば試してみてください。
”人間の言語習得のメカニズムについての認知心理学的言説、及び、言語学的言説について、代表的な言説を3つ程度教えてください”
2.外国語習得についての理論
代表的な理論は、以下の通りです。
1.インプット仮説(理解可能なインプット、現在の能力より少し上のレベルのインプットが重要)
2.アウトプット仮説(インプットだけでなく「アウトプット(話す・書く)」が習得を促進する)
3.インタラクション仮説(相互作用的なコミュニケーションの中で促進される。学習者は相手とのやり取りを通じて誤解や理解のズレを修正する)
実際の英語指導でもこれらの理論に基づいた指導が行われています。ただし、私には常識を並べているだけの言説と思えます。私が大切にしている理論は、Carroll の理論(注:1962)です(注:Carrollの研究は冷戦下の米国で外国へのスパイを効率的に育成するために行われた背景があると言われています)
Carrollは、『The Prediction of Success in Intensive Foreign Language Training』において、外国語習得に必要な適性(言語適性)を以下の4要素に分類しました。
-
音韻符号化能力 (Phonetic Coding Ability):音声を正確に知覚・記憶し、再生する能力。
-
文法感覚 (Grammatical Sensitivity):文の中で語の文法的役割を把握する能力。
-
帰納的学習能力 (Inductive Language Learning Ability):言語規則を観察から導き出す能力。
-
記憶力 (Associative Memory):単語や意味を関連づけて記憶する能力。

この理論には多くの批判があります。主な批判は以下の通りです。
1.過度の認知能力依存:Carroll のモデルは学習者の「認知的スキル」に大きく依存しており、情意要因(動機づけ・態度・不安)や社会的要因(相互作用・文化環境)をほとんど考慮していない
2.教育・教授法の影響を軽視:Carroll の理論は「学習者の能力」を前提としすぎており、教授法・教材・学習環境の違いによる学習効果の差を十分に説明できない
3.第二言語習得研究の発展との乖離:1960年代以降の研究(クラッシェンのインプット仮説、スウェインのアウトプット仮説、ロングのインタラクション仮説など)は、言語習得を「動的・相互作用的プロセス」として捉える方向へ進みました。Carroll の適性構成要素は、静的で測定可能な「個人差能力」を強調しすぎている
4.テスト偏重の問題:「適性テスト」に基づく研究は、学習成果を予測するうえで有用ではあるものの、テストのスコアが「本当に言語運用能力を反映しているのか」という疑問があります。特に実際のコミュニケーション能力(発話の流暢さ・文化適応力)は、適性テスト の測定範囲外
これらの批判は納得的ですが、それを理解した上でも、私がCarrollのモデルを重視している理由は、この理論が、外国語習得者の個性を理解する上で参考になる切り口を与えているからです。例えで説明します。

1.「野球でカーブを投げるにはどのように練習したらいいか?」との問いに対して、物理学的になぜカーブが投げられるかを理解します。物理学的には力学、液体力学の分野(マグナス効果)で説明できます。ボールの回転による空気の流れの変化=空気抵抗(圧力)の差が、ボールの動きに影響を与えるということです。外国語の上達では、1の言語習得についての認知心理学・言語学的理論の理解の部分です。
2.1の理解はできても、カーブを投げられるようになるためには練習が必要です。カーブを投げられるために必要な練習量は一人ひとりで異なります。練習法も異なります。カーブを投げるという目標に対して、一人ひとりの個性を理解して指導することが上達をうながす秘訣です。これは、外国語の上達では2の言語適性に当たります。音声に敏感な人、文法センスのある人、記憶力。それぞれ一人ひとり違います。練習後すぐにカーブを投げることができる人もいますが、何度も練習が必要な人もいます。肩、指先の使い方を段階を追って細かく練習することが上達への早道の人もいれば、全体をまとめて練習することが適切な指導となる人もいます。一人ひとりの個性を理解した指導が必要です。
3.外国語習得の理論にあるような”一般的な”解決法は、集団への最大公約数的教育に当てはめることはできるかもしれませんが、一人ひとりへの効果とは別問題です。一般解ですから、内容もあまりに常識的過ぎて実際的な解決策にはなりえません。
4.一人ひとりの個性を考える上で、一定のフレームワークを持って考えることで、解決策への近道になることがあります。まず、フレームワークを通して目の前の個人の個性を考え、その上で一人ひとりの解決法を探ることで、早く解決につながる可能性が高まります。
これらを考えると、Carrollの理論で抽出された要素を理解した上で生徒の個性を考える事が効果的という結論になります。
3.大学受験での英語という視点での実際的な学習
上記の1.2を踏まえた上で、実際的な学習指導法を考え、実践することが学問ノススメの責任です。その際に大切にしている考えは、3つあります。
a.母国語ではない言語であること
b.言語習得には一定のロジックがあること
c.学習者の個性
上記のbとcは、それぞれ上記の1と2で述べたことです。ここでは、実際的な学習指導法を考える際の視点としてa(母国語ではない言語であること)について説明します。

1.生活の中で習得することはできないことを意識した指導
母国語のように、生活の中で繰り返し練習して習得することは英語ではできません。効率的で効果的な方法を見出す必要があります。その際に、参考にしている軸は2つです。
1.日本語との違いから英語の特徴を考えること、
2.ネイティブスピーカーはどのように英語を習得し活用しているか
詳しくは以下のブログにまとめています。
大学受験 英語学習法 その2(文法・語彙実践編)~認知心理学、外国語習得の視点~
大学受験 英語学習法 その3(ネイテイブスピーカーの英文法、スキーマ)
1つ目の要点は、日本人が陥りやすいミスを先回りして指導すること、合理的な学習順序を守って指導することです(この点は、本シリーズの第1回でAIも解答しています)
2つ目の要点は、ネイティブスピーカーの英語の学びには英語の特徴を踏まえた学び方が自然と確立していることです。その学習法の要諦を言語化して生徒に伝えることです

2.うまくなりたいという意識
最後に、生徒に求められるものは、うまくなりたいという気持ちと努力です。これがない人は上達しません。カーブを投げるためには、練習が必要です。上達したいという気持ちがあり努力があって初めて、効果的な指導法を生かすことができます。
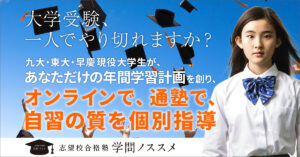
(注)学問ノススメの個別指導の無料体験をして頂くことで、学問ノススメの受験勉強へのアプローチや考え方、個の指導を実感して頂けると思います。どうぞお気軽にお問い合わせください。
(文責:大井 筆者略歴はコチラ)