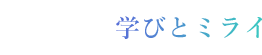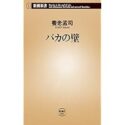英単語の謎に迫る ~学習効率を高めるための言語学的アプローチ~
- 2025.11.14 | 九州大学 高校生・受験生の学び(現在) 大学での学び(近い未来)
九大の知と社会をつなぐ
九大は社会連携事業として多くの取組をしています。「九大の知と社会をつなぐ」をテーマに、以下の様々な取組があります。
・福岡県・福岡市、九州各県をはじめとした地方自治体との連携活動
・市民公開講座
・研究者が日々の研究内容を市民に分かりやすく伝えるイベント

(九大社会連携事業HPより)
社会への積極的な働きかけ(アウトリーチ)として、”サイエンスカフェ@ふくおか” (注)があります。
(注)サイエンスカフェ@ふくおかは、講師と参加者の距離感を出来るだけなくし、気軽に参加でき気軽に質問できるイベントです。子どもから大人まで、参加者全員が科学を楽しめるように毎回工夫しながら開催しています。(サイエンスカフェ@ふくおかのHPより)先日、サイエンスカフェ@ふくおかのイベントに参加してきました。
 (サイエンスカフェ@ふくおか HPより)
(サイエンスカフェ@ふくおか HPより)
「英単語の謎に迫る!」~学習効率を高めるための言語学的アプローチ~
内田諭 准教授(九州大学大学院言語文化研究院・地球社会統合科学府・共創学部准教授)による講義、参加者(学生、教育者)とのデイスカッション(90分)でした。内田先生の専門は、「英語学(認知意味論、コーパス言語学、語用論)、応用言語学(辞書学、英語教育学」です。内田先生は、権威ある学術雑誌(Studies in Second Language Acquisition(SSLA)2024年のGoogle ScholarでLanguage and Linguistics分野で1位にランク)に論文が掲載される研究者です。一方で、実用的な英語上達本(TOEIC対策本)も執筆されています。

(サイエンスカフェ@ふくおか HPより)
イベントでは英語を学ぶための実用的なヒントをいくつか頂けました。印象に残った内容は、「語源や共起語(ある言葉とよく一緒に使用される言葉)」を勉強することで、英語のレベルが上がっていくということです。AIがいろいろな解答を瞬時に行う方法論は共起語を探して解答することです。生成AIのモデルであるLLMは「大規模言語モデル(Large Language Model)」の略で、大量のテキストデータをディープラーニングで学習し、人間が使う自然な言語を理解・生成する技術です。AIのこの学習法は、元々は人間の言語学習を参考にしています。私たちが外国語を学ぶ上で、AIの学習法を意識する必要性をわかりやすく説明されていました。また、実用的な情報として、Corpas(注1)の紹介や、英作文の添削ツール CWLA2(注2)を紹介して頂きました。

(英作文評価ツールの一例:九大2025年過去問英作文模範解答について)
(注1):コーパスとはLLMが学習する際に使用される大量のテキストデータセットのこと。実際に話されたり書かれたりした自然言語(日本語、英語など)のテキストを大量に集め、コンピュータで検索・分析できるように整理したデータベースです。
(注2):10語から800語までのテキストを入力すれば、英語学習者の語学レベル(CEFR-J:preA1、A1.1、A1.2、A1.3、A2.1、A2.2、B1.1、B1.2、B2.1、B2.2、C1、C2)を推定します。、主に高校レベルの作文を対象としています。2025年の九大二次試験 英作文の模範解答を入力すると、レベルはB2(英検準1級レベル)、自然な英語表現のアドバイス・文法上の誤りを4か所指摘していました。
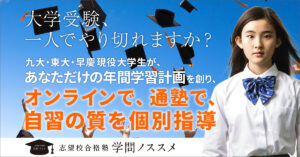
内田先生は、来年初めに、英語学習法についての攻略本を出版する予定とのこと。是非、注目してください。
(文責:大井 安治)
筆者略歴;合同会社ミライノ 代表社員 「志望校合格塾 学問ノススメ」(高校生向けオンライン個別指導、福岡教室での個別指導)を経営。京都大学 法学部卒業(1983年)、臨床発達心理士、税理士。詳しい経歴はコチラ。