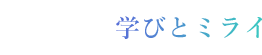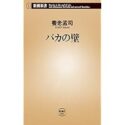国際交流プログラム(かめのりカレッジ)報告(2025年8月開催)
- 2025.10.17 | 大学での学び(近い未来)
かめのりカレッジ
5月にご紹介した、国際交流プログラム(”かめのりカレッジ2025")が8月末に開催されました。かめのりカレッジ(Kamenori College)は、かめのり財団(注)が主催する国際交流プログラムです。
(注)同財団の設立趣旨:「日本とアジア・オセアニアの若い世代の交流を通じて、未来にわたって各国との友好関係と相互理解を促進するとともに、その架け橋となるグローバル・リーダーの育成をはかります」
Kamenori Collegeは、様々な国際交流の機会において存在感を発揮し、自己主張可能な人材を育成することを目的としたプログラムです。「国際的な視野の拡大」「現状の英語力での発信力の強化(マインドセットの強靭化)」「クロスカルチャー環境の体験」「プレゼンテーション・スキルの向上」の4点を柱としており、将来に向けて自己の変革と成長に意欲の高い学生の参加を求めています。(かめのり財団ホームぺージより)
今回、学問ノススメの卒業生及び講師各1名が参加者に選抜されましたので、私も様子をうかがってきました。

開催概要(かめのり財団ホームページより抜粋(一部修正)
日本とアジア4ヶ国(フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ)からの大学生、合計22名が東京都内に集まり、2025年8月24日(日)~8月27日(水)まで、3泊4日のメインプログラムが行われました。プログラム中はセッションをはじめ、チームワークショップ、プレゼンテーションも全て英語で行われました。参加人数は、国内在住の大学生18名及び東南アジアの大学生4名(インドネシア、フィリピン、マレーシア、タイ)です。
KC2025テーマ:「Change Yourself」
3つのルール:① Step out of your comfort zone!② Don’t be afraid to fail!③ Speak Out!
事前プログラムとして、7月19日(日)にオリエンテーションをオンラインで行い、全国各地から選抜された大学生と、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシアからの海外生が顔合わせ。初回のチームディスカッションが行われました。メインプログラムまでの間、学生たちはチームごとにオンラインで集まり、ケーススタディの理解と議論を重ねました。事前プログラムの一環として、英語グループレッスンも並行してスタート。7月末から8月末まで、少人数(1グループ4~5名)にわかれ、英語での発信力の強化レッスンが、オンラインで行われました。約1ヶ月の事前プログラムを経て、2025年8月24日(日)から、東京で3泊4日の合宿がスタートしました。

メインプログラムでは、様々な専門分野の講師による講義と、チームでのワークショップを経て、最終日にチームプレゼンテーションが行われました。KCのセッションは、ただ聞くだけではなく、参加型のセッションです。グローバリゼーションとは何か、環境のために自分たちが出来る事は何か、世界での日本の位置など、講師から与えられたテーマについて議論し共有しながら、考えを深めていきました。また、最終日のプレゼンテーションに向けて、必要なスキルも具体的に学び、練習を重ねました。

最終日のプレゼンテーションの内容は、「コンサルタントとして、顧客が抱える問題の分析、根本的な原因、解決方法を提示すること」内容に加えて、プレゼンテーションスキル、チームワーク等も評価の対象となります。講師・参加者全員からの投票によりベストチームが決定し、クリスタルの地球儀が送られました。最後に修了証書が渡され、KC2025は終了しました。
意見がぶつかり合いなかなか話が進まなかったり、衝突したり、チームとして上手く機能するにはどうしたらよいか等々、悩み考えた 4日間。英語になると伝えたい事が伝わらず、語学力を見直す機会にもなったようです。睡眠時間を削って作り上げたプレゼンテーションも、思うように発表できずに悔しい思いをした学生もいましたが、ここで経験した失敗や悔しさを糧に、出会った仲間との縁を大切に、世界にはばたいて欲しいと願います。

参加した学生からの声は以下の通りです。
・チームのメンバーと必死になって考え、協力し、議論し、1つのものを作り上げるという貴重な体験ができた。意見がぶつかり合ったり、考えが全員でまとまらなかったりと、衝突する場面も多かったが、そんな衝突をどのように乗り越えたら良いか考える機会となった。
・大学生活において、1つのことにこんなにも熱中したことはあまりなかったので、自分自身を変える良いきっかけとなった。
・何も恐れずに挑戦できる環境はとても貴重だったので、ありがたかった。
・たった 4日間の短い時間であったが多くを学び、異なるバックグランドで似たような目標、夢をもち似ているようで異なる価値観を持っている人と触れ合うことができ自分自身の考えを改めることができた。
・自分の価値観も悲観的にとらえていたものが肯定的にとらえるようになったものが多々あった。毎日メンバーから刺激を受ける日々で自分にとってとても貴重な経験になった。
・同じ時代を生きる同世代の仲間との出会いは、私を大きく変えてくれました。まだ自分には伸びる余地があることに気づけました。

所感
プログラムの内容は、社会人として身につけるスキル研修(リーダーシップやコミュニケーションスキル)や、英語でのデイスカッション・プレゼンテーションで、合宿前の事前課題や英語研修がオンラインで用意されており、大学生にとっては良い気づきの機会になっているようです。このプログラムを立ち上げたリーダーが、私の昔の職場の知り合いという関係で、昨年参加者選考に関係する機会があり、参加する大学生数十名と面接をしました。その際の感想は、以下の通りです。
1.全国の多様な大学生(北海道から九州までの幅広い大学)との交流・学び(インターカレッジ)
2.社会人・大学教授からの実践的スキルの学び(就職活動に活かせる)
3、英語でのコミュニケーションをせざるを得ない環境(アジアからの大学生とのグループワーク・デイスカッション・プレゼンテーション)
そして、今回メインプログラムでの学生たちのチームプレゼンテーションを拝見して強く感じた言葉は、「Step out of your comfort zone!」です。大学生にとって、英語のみでの議論、プレゼンテーション。初対面のメンバー、異文化の国内外のメンバーとのチームビルディング。決して、快適な環境ではないはずです。閉じこもらず、失敗を恐れず前向きにチームに貢献する姿勢。社会に出てから必ず経験することです。短い期間ですが、彼らにとって貴重な機会になったと思います。心理学者のクルト・レヴィンが提唱した理論で「場の理論(Field Theory)」があります。人の行動には、その人の特性と周囲の環境が関係しているという理論です。怖いけど、自分の場(柵)から脱出する、そこから新しい自分自身が生まれる可能性があります。
海外留学という選択肢を2025年5月に紹介しましたが、アンテナを張っていればいろいろな機会があります。大学生活とはそういうもの、社会への扉です。受験生のみなさんも、受験後の近い未来に目を向けていると、自分を変える機会に巡り合えるチャンスはきっとあると思います。
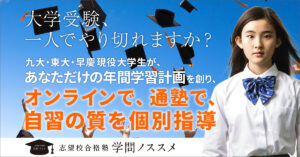
(文責:大井 筆者略歴はコチラ)